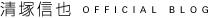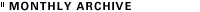弾 DAN2
僕は駅で列車を待っている。
ただじっと、木製のベンチに座って下を向きながら。
駅は古くてとても清潔とは言えないが、周辺に緑が生い茂って空気も新鮮だ。
単線の典型的な田舎駅で、改札口に駅員もいない。
駅はその殆どが木の素材で作られており、そのためか目に付くものが殆ど茶系の色だった。
薄い茶色から濃い茶色、赤茶、こげ茶など、様々な茶色がそこにはあった。
そんな駅の周辺には僕の背丈くらいある草や駅の屋根より遙かに背の高い木が駅を取り囲むように生い茂っており、コップからあふれ出す水のように駅や線路にはみ出していた。
季節は夏だ。
セミが切なくなるほど勢いよく泣いている。
「鳴く」ではなく「泣く」にきこえる。
気温は熱く、日差しは刺すようだ。
しかし、どこからかいつも水の流れる音が聞こえてくるし、それほど湿気を感じない場所なので、耐えられないような暑苦しさは感じなかった。
僕はこの駅から一歩も外に出たことがないので、その水音が川なのか何なのか分からなかったが、それがとても冷たい水でとても新鮮な透明水だという事は何故か想像出来た。
そんな環境で僕はもう何年も列車を待っている。
ただじっと、木製のベンチに座りながら。
駅には他の乗客がポツポツと何人かいた。
僕らは互いに話したことは一度もない。
時々チラッとお互いを見合うことはあるが、コミュニケーションと言えるものはそれくらいだった。
あるいはそれはコミュニケーションではなくて、単なる状況把握のような感じもした。
お互いを干渉しない事、それがこの駅のルールのようなものになっていた。
だから、僕らはもう何年も誰とも口をきいてない事になる。
しかし、それは苦痛じゃなかった。
それが苦痛ならこの駅にはいないという事を僕らはよく理解していたからだ。
この駅にいる者は皆うつむき加減で暗く、いつでも何かに疲れたような雰囲気が感じられた。
でも、セミの声がその憂鬱な雰囲気を打ち消してくれていた。
それに、僕らは好きでここにいるのだ。
列車を待つと決めた時から、僕らは自らの意志によってこの駅で待ちぼうけをしている。
だから、列車がいつまでも来ない事に対して普遍不満を言う人は1人もいなかった。
僕らは、正確に言うと列車を待っているのではないのかもしれない。
列車がこの駅に到着する日を待ち望んでいるのではない気がする。
僕らはきっと、まちたいのだ。
殆どの人間は列車が来るまでの待ち時間を外で暮らしている。
ある者はくたくたに疲れるまで遊んでいるかもしれない。
ある者は息を切らして働いているかもしれない。
僕ら以外の人間はこの駅の外で生きる事を選んでいる。
そして、僕らはこの駅の中で列車を待っている。
どちらにしても列車をまっている事に変わりはなかった。
しかし、その待ち方が違うのだ。
列車は駅に到着すると、全ての人が乗り込むまで待ってくれる。
何時間でも何年でも待ってくれる。
つまり、この列車に乗り遅れる人はいない。
だから、この駅で待つのは馬鹿馬鹿しく感じる人の方が多いのであろう。
その事実を知った上で、僕らはこの駅で待つ事を選んだ。
それはある人からは「異常」だと思われた。
ある人からは「怠け者」だとも思われた。
僕ら駅で待つ人間を外界の人間はあまりよく思わない。
暗くて気味が悪いし、一緒にいて楽しくない。
だけど、僕らは誰1人として異常者はいなかった。
むしろ、みんな普通過ぎる程普通で、凡庸を絵に描いたような人々だった。
考えることは一般論だし、意見はいつも「人それぞれ」だった。
それでも、外界の人々は僕らが駅にいるという事だけで僕らを嫌った。
僕らはそれでも良かった。
僕らへの意見や僕らの見方というのは、彼らの問題である。
僕らの中にある問題じゃない。
僕らの外の問題だ。
丁度、この駅の内側と外側のように、そこにはしっかりとした境界線があった。
一般論というものは、多数派の意見によって決まる。
少数派は意見すら言う余地がない。
それが外のルールだ。
しかし、僕らは一般論がそういう風に決まるべきではないと思っていた。
僕らの中では、一般論とは、他人に迷惑をかけない理論の事を指していた。
多数派の意見が一般論になる世の中では生きていけない事をよく理解していた。
もし迷惑なら、直接迷惑な事を指摘すればいい。
そこには批判なんて必要ない。
苦情も必要ない。
勿論それは相手に悪気がない場合だが。
ゴドンゴドン、ゴドンゴドン。
列車が通過した。
通過列車には「事故死車」と書かれていた。
その乗客達はみな悔しそうな表情をしていた。
僕は何かを思い出そうとしていた。
この駅で待っている内に、何か大切な事を忘れた気がしたのだ。
僕は僕の記憶の宇宙を彷徨ってみる。
しかし、そこには明確なものが殆どない。
あるのは記憶の影とそれらの気配だけだ。
仕方ないから僕はちゃんと思い出せる事だけを考えてみる。
記憶の宇宙を旅して、ちゃんと認識出来る事はそれほど多くないという事に気付いた。
記憶というものは時の流れのように一つの場所に留まってはくれないのだ。
現在というのは、未来に喰われるものだ。
現在というのは、過去を喰うものだ。
現在とは未来とも過去とも言えるのかもしれない。
記憶とは、過去にある現在だ。
それはまた、未来とも過去とも言えるのだ。
だから、正確に感じられる事なんて記憶の中には一つもない。
過去の現在は、現在の現在にはなれない。
でも、僕は過去の現在を出来るだけ忠実に再現しようと試みる。
宇宙の中で光が少し漏れている扉を探し、そのために気が遠くなるような距離を移動する。
そしてやっと一つだけ扉を探し出した。
あれは6月の事だった。
僕は梅雨の合間に時折現れる太陽を懐かしそうに眺めていた。
土からはまだ雨の匂いがしてくる。
刺すような日差しに手をかざしてみると、指先が赤く光った。
指の中に赤い果物が入っているかのように明るい甘い色だった。
僕は木漏れ日の中に入って、今度は木漏れ日を感じていた。
目を瞑って風にゆられる木々を感じると、肉眼で見るよりずっとリアルだった。
僕は目を瞑る事で別世界に行ける。
風景やルールは一緒の世界だが、その別世界には僕しかいない。
本当の孤独を感じる事が出来る。
僕はその内に目を瞑っていても木々の揺れが分かる事に気付いた。
それは小学6年生の僕にとっては一大事だった。
超能力を身につけたような気分だった。
僕は暫くそうやって風と光を感じていた。
すると、横から何かが僕にぶつかった。
僕は車に轢かれたのかと思った。
痛みはなく、全てがスローに感じた。
僕はすぐ横にあった階段を転げ落ちていった。
10段くらいの階段だったのだが、100段くらいあるかのように感じた。
落ちきった所で、僕は痛みを感じた。
感じたというよりは、痛かった事に気付いたと言った方が当てはまるかもしれない。
あの時僕が何に当たったのか、よく思い出せない。
ゴドンゴドン、ゴドンゴドン。
駅にまた通過列車が走った。
今度は「自殺車」と書かれていた。
中にいる人たちはとても悲しい表情を浮かべていた。
僕はその列車が見えなくなるまで見ていた。
列車はとても混んでいた。
ぎゅうぎゅう詰めだった。
あの時僕は何に当たったんだろう。
また何かを思い出しそうだった。
ぎゅうぎゅう詰めの列車…。
確かあの時僕は満員電車の中にいるような思いをした気がする。
沢山の足音、息が出来ないような混雑…。
その時僕の脳を電流が走った。
まるで雷が脳の中で発生したかのように。
そして僕は鮮明な記憶を呼び起こせた。
そうだ。
あの時、僕は車に轢かれたんじゃない。
人に蹴られたんだ。
蹴られて転げ落ちた。
そして、落ちた後に30人もの同級生にリンチされた。
踏まれたり、蹴られたり、殴られたり、引きずられたり…。
でも、僕は痛みを受け入れなかった。
痛みの存在を信じない事で痛みを感じなかった。
目を瞑れば、別世界に飛ぶ事が出来る。
そこでは、同じ情景同じルールだけど僕は孤独だ。
だから、リンチにあって痛みを感じる事はない。
僕は別世界に逃げた。
体は泥まみれになりながら、僕は魂だけの存在になった。
僕を馬鹿にして笑う声も、僕を蹴る足音も、もう何も存在しない。
気が遠くなる。
光が僕を包み込む。
気がつくと僕はこの駅にいた。
それからずっと僕は列車を待っている。
死という列車だ。
ただ、待つだけの人生を送っている。
しかし、僕は大切な事を忘れている。それが何だったか、僕には思い出せない。
きっと、この駅を出れば思い出すのだろう。
そんな気がする。
だけど、僕はここでじっと列車を待つのだ。
それが、僕の人生だから。
つづく