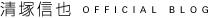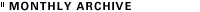12歳のぼく
その日僕はまたレッスンで叱られた。
高いレッスン費を払って通うのだが、通用しないからと言われ門前払いにされる。
「これじゃあレッスンにならない」
とため息交じりに冷たく言われ、先生は黙りこくってしまう。
そして永い沈黙が訪れる。
この沈黙は、小学校の朝礼での校長の挨拶より永い。
そして、宇宙に一つブラックホールが出来てしまうくらい重い。
その沈黙の後、僕は自主的に荷物をまとめ、先生の前から一刻も早く消えなくてはならない。
かくして、今日も僕は逃げるように先生の前から掛け出てきた。
いつまで僕は門前払い族なのだろう…。
5分で終わってもいいから、レッスン費だけは返して欲しい。
そんな事を考えながら帰りのバスに乗り、揺られ、揺られ、揺られ。
バスは駅に着き、僕はここから電車に乗り換えて帰る事になる。
バス停を降りてから駅までは歩いて30秒だ。
もう、駅のすぐ目の前にバスは到着する。
その30秒の距離の間にカフェが一軒ある。
そのカフェに入ったことはないのだが、その日は何故かとてもこのカフェが気になった。
なんともない普通のカフェなのだが、焼きたてパンの良い香りがする。
僕は暫くそのカフェに入ろうか迷った。
そして、ある視線に気付いた。
その視線は僕の方に一直線に伸びてきていて、僕の脳天を直撃し貫通していた。
僕はその視線をさっきから感じていたのだと把握する。
カフェが気になったのではなく、視線に気付いたのだ。
その一直線の視線を辿っていくと、その奥にはおじさんがいた。
薄い茶色のコートに、同じ色の紳士帽を被っていた。
おじさんは僕に優しく微笑みかけ、そして僕に手招きをした。
僕は迷わずおじさんの所に向かった。
僕がおじさんの所に到着すると、おじさんは「やあ」と右手をあげた。
「随分待っていたよ」
僕は不思議とそのおじさんがここで僕を待っていた事を知っていたような感じがした。
「でも、レッスンは5分で終わったのでそれほど待っていなかったのではないですか」
と僕が言うと、おじさんはふぁっふぁっふぁと面白い笑い方をした。
僕はカフェオレを頼んで、それを飲んだ。
おじさんはもう飲み終わってしまったカップをずっと自分の目の前に置いていた。
暫く沈黙があった後で、おじさんは茶色の鞄から真っ白な紙を出した。
そして何やらその白い紙で折り紙を始めた。
慣れた器用な手つきでおじさんは折り紙を折り、その折られている折り紙は、
みるみるうちに飛行機へと変化していった。
「はい!飛行機一丁おまちぃ」
とおじさんは僕に陽気に告げてその飛行機を手渡した。
「ありがとうございます」
と僕は良い、その飛行機を受け取った。
「紙飛行機はいいぞ。燃料も使わない。地球に優しい。
で、人間が自分で飛ばすから、人間のエネルギーは要する。
ダイエットにも良いし、ストレス発散にもなる。
ほら、その飛行機に嫌な人の名前を書いて飛ばしてごらん。
明日からその人は君の人生からいなくなるから」
僕は少し怖くなった。
「いえ、それほど憎い人はまだいません」
おじさんはそれを聞いて少し残念そうだった。
「そうか。それじゃあしょうがないな。まあ、いずれこれを使う日がくるだろうし、
持ってってくんな。いいだろ?使わなきゃ使わないでいいんだ。
とりあえず、持って行きなって」
かくして僕は紙飛行機を持ち帰った。
おじさんは僕に紙飛行機を強引に渡した後、急に席を立ってどこかに消えてしまった。
消えるように人波に紛れていったのではなく、本当に消えてしまったのだ。
どうやって消えたのかはよく覚えていない。
とにかく、煙のようにどこかに漂って行ってしまった。
カフェの自動ドアは開かなかったし、店員も何も反応しなかった。
もしかしたらおじさんは僕の見た幻覚なのかとも思った。
しかし、僕の手元には紙飛行機があったし、
テーブルにはおじさんが飲んだであろう空になったコーヒーカップがあった。
勘定は僕の分まで払われていた。
僕はその紙飛行機を帰って自分の部屋で何度も飛ばしてみた。
勿論誰の名前も書いていない。
しかし、白紙の紙飛行機を飛ばすと、世界のどこかで誰かがいなくなっている気がした。
何だか少し怖くなった。
僕はこの折り紙飛行機を信じている。
いや、あのおじさんを信じている。
信じるしか僕には選択肢がないように感じる。
僕は僕の名前を書いて飛ばすつもりだ。
人が消えるとき、何を感じて何を見るのか。
それが知りたいし、誰か消すなんていう下らない事よりは、ずっと面白い。
でも、まだその時じゃない。
まだその時じゃない。
きっと、消えた向こうの世界には、おじさんが門番をしている世界がある。
それは、もの凄く簡単な移動だと思う。
コンビニ行くよりはずっと楽だろう。
そろそろ夕暮れだ。
光が闇に押し出されようとしている。
しかし、それは光が闇に負けたからじゃない。
ただ、交代して世の中を見守っているだけなのだ。
明日の朝は、どんな朝だろう?
未来は「未だ来ず」と書く。
今は過去となり、未来が今となる。
それを繰り返し繰り返し僕は生きている。
十年だって十五年だって、同じ事の繰り返しの結果そこにいきつくのだ。
浜松で東海道を見つけたとき、この道が東京に繋がっているのだと思った。
遠い遠い道のりではあるけれど、この道を辿れば、東京に帰れる。
僕は人生のようだと思った。
これから僕はどうなるのだろう?
いつかはピアニストになってCD出したりコンサートが出来たりするのだろうか?
不安だ。
怖い。
でも、最後の手段で僕は消える事が出来る。
だから、大丈夫だ。
消える事はとても簡単だから。
でも、それは最後の手段だ。
飛行機は最後まで使わないでおく。
そして、25歳の誕生日に、僕はその飛行機を燃やした。
もう、僕にその飛行機は必要ないのだ。