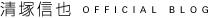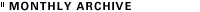弦打楽器の友達
狭い楽屋の一番端っこで、壁と同化したくて、呼吸もろくにせずに座っていた。
僕は、ずっとこうやってじっとしていれば、
そのうちこの狭い部屋の「角の一部」となれると思っていた。
そう、壁になって、僕は消えるんだ。
「出番です」とスタッフがこの部屋を訪れる時には、僕は既に壁の一部となっている。
それで、この心臓が違う生き物のように激しく膨らみは縮んでいる現象も何ともなくなる。
それで、僕は何も弾かなくてよくなる。
このピアノ地獄から逃げ出せる。
かくして、僕はもう二度とコンクールに出る事もなく、この大阪にあるホールの楽屋の一部となって、一生を気楽に、のんびりと暮らした…
とはいかない。勿論。
壁の一部になってもうすぐ来る出番を逃れる、という変人的な妄想をしていると、案の定素晴らしいタイミングでスタッフの人が僕の楽屋を訪れた。
「出番ですよ」
僕は、心の準備が出来ていないまま(というか現実逃避しかしてない)、
ステージに放り出された。
仕方なくピアノの鍵盤に手を置いて、一音目を義務的に出してみる。
なんだか空っぽだ。
どうしてピアノを弾いているのか、何故ここにいるのか、全く意味がわからない。
しかし、動きの連続で、手が勝手に弾いている。
そこには丸で心はない。
あるのは体だけだ。
心はまだあの楽屋にいる。
体だけが焦ってステージに出てきてしまって、心がまだついてきていない。
手だけが感情と意志を持って一生懸命に動いている。
そんな不思議な現象を僕は目の当たりにしている。
幽体離脱のように不思議だけど、これを非現実だと思ってはいけない。
「こんな事あるわけない」
なんて思ってしまうと、とたんに魔法はとけてしまう。
本当に非現実になってしまうのだ。
だから、今目の前で起こっている嘘のような本当の現象を、
心から受け止めなくてはいけない。
無心。
それだけが、心がこのステージに遅れて出てきてくれるまでのポイントだ。
5分もすると、やっと遅れて心がステージに来てくれた。
よし、これでもう大丈夫。
後はいつも通り弾くだけだ。
何百回、いや何千何万回と弾いた。
後は、いつも通り…
え?いつも通りってなんだ?
いつもどうしてたっけ?
もうすぐ一番の難所が待ち受けている。
どうしよう、このままでは、いつも通りがわからないから、どうしていいか分からない。
あの難しい場所を、どうやって弾けば良いんだ。
あぁ、もう後5章節くらいで難所が来てしまう…。
…4.3,2,1。
「えい、こうなったらもう何でも良い、思い切りやってしまえ!」
その後の記憶はあまりない。
この間、たったの12分。
この12分のために、1年間全てを費やしてきた。
一度きりの挑戦で、二度目は絶対無い。
人生で、絶対に一度のチャンス。
そして、このコンクールで優勝しなきゃ、もうピアニストになれないと、言われている。
「死んでも良い」
矛盾しているけど、中学2年生だった僕は、このチャンスを手に入れられるならば、
死んでも良いとさえ思っていた。
ドラゴンボールに願いを叶えてもらえるならば、かわいい女の子でも、永遠の命でもなく、
このコンクールに優勝したい、という願いだった。
その本番だ。
予選も準決勝も勝ち抜いた。
後は、このファイナルだけだ。
その演奏を今していて、もうすぐ終わる。
そうだ、僕の人生が終わる。
それくらいの勢いだ。それくらいの感覚を持っている。
…あ、そんな事を考えているうちに、もう少しで終わる。
そう、この和音が出てきたら、あとこうして、ああして、こうやって、ちゃんちゃん。
終わり。
心は落ち着いているけれど、体がおかしい。
視界が黄色い。酸素不足だ。
立ち上がってお辞儀しなくてはいけないのに、足に力が入らない。
全身がけいれんしていて肺が痛くて心臓も痛くて腰のあたりの感覚がなくて左足が…
ようやく立つと、そんな僕の苦労もしらずに、審査員達が偉そうに頷いたり無視したり視線をわざとらしくそらしたり何だか知らないけど紙にメモしたりしている。
「もうやめよう。もう終わったんだ僕。いいんだ。もう泣いて良い。壁になったように、
一生を眠って過ごそう。もう、終わりだ。二度とステージには上がらない」
いつもいつもそう思ってた。
落選するくらいなら死んだ方がましだ。
そんな意識が呪いがとけないから、僕はいつも苦しんでいた。
12時間も13時間も練習しても、その呪いはとけない。
眠れば夢に出てくるし、起きれば散歩をねだる犬の遠吠えのように僕を催促する。
それでも、好きだから、未だにピアノを弾いている。
もう、何百年も弾いているような感覚だ。
そんな事を考えていたら、荒川さんと村主さんが氷の上で回っていた。
ジャンプの直前に見せるあの表情。
硬直して、一瞬体と心が遅れて見える。
ジャンプしながら回転している体の後を、そのまま心が沿って動いて残像になっている。
あの時の僕と同じだ。
だから今回一緒にCDを作れてよかった。
僕が弾く。あなたは回る。
わたし、配る。
…は武富士だったか。
笑止