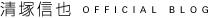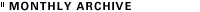乗り換えの途中、「お腹空いたなぁ」と呟きながらふと横を見ると、売店があった。
「ぐぅ」と、絶妙なタイミングで腹時計が鳴る。
僕は本能的に食べ物に見入ってしまった。
どれくらいそれを欲しそうに見ていたら、赤の他人がそんな親切をしてくれるのだろう?
すぐ後ろに立っていたロシア人のお婆ちゃんが、僕にアイスクリームを買ってくれたのだ。
何やらロシア語でしゃべっているのだが、全く解らない。
でも、僕にはそれが「優しい言葉」だという事だけは解った。
両手が荷物で塞がっていて、僕はお婆ちゃんが買ってくれたアイスを受け取れなかったが、お婆ちゃんはアイスを袋ごと強引に僕の鞄に入れた。
僕はお金を盗られていないか心配になって、すぐに鞄を確認した。
…お金は無事だった。
しかし、そうこうしている内に、また1本電車を見送ってしまった。
お婆ちゃんはその電車に乗って行ってしまったので、ろくにお礼も言えなかった。
「悪い事したなぁ。でも、親切な人もいるものだ」
と、僕は改めて人の温かさを知ったのだった。
僕が乗り換えに手こずっている間に、辺りはすっかり暗くなっていた。
USドルに両替した入学金と、血液検査の結果を、何とかモスクワ音楽院に持って行けたのはいいが、その夜泊まる所をまだ手配していない。
モスクワの夜は、閉め出されたら終わりだ。
僕は、面倒臭がる音楽院のスタッフを何とか説得して、急いでその日泊まる所を紹介してもらった。
紹介してくれたのは、どうやら音楽院の「寮」らしい。
噂では寮は酷いところだと聞いていたので、ちょっと不安だったが、こうなったらもう何も怖くない。
屋根があって風が凌げるだけでも充分だ。
僕はすぐに紹介された寮に向かった。
白タク(お金の要るヒッチハイクのようなもの)で随分安く値切ることに成功したが、酒瓶を片手に運転していた事は、苦笑するしかなかった。
かくて寮に無事たどり着いた頃には、モスクワに夜が訪れていた。
悪臭とゴミにまみれた寮だったが、それでも僕は、ここまで辿り着けたという達成感を覚えていた。
「強くなったな」
と鼻で笑いながら、何とか自尊心を保ってみる。
元々が「苦しい体験」をしたくて日本を飛び出てきたのである。
辛いと感じながらも、僕はどこかで満足感を感じていたのかもしれない。
やがて、寮母さんが僕の部屋に案内してくれた。
そこは冷蔵庫みたいな寒さだった。
管理人の寮母さんは、全く外国語が解らなかった。
僕が言う英語もまったく通じない。
何やら、怒っているようにロシア語を機関銃のように喋ってから部屋を出て行ったが、僕はもうバカにされるのも問題を起こすのも懲り懲りだったので、笑顔で「ダーダー」と言っていた。
ダーとはロシア語でYESという意味である。
しかし、後々知った事だが、その時寮母さんは僕に大切な説明をしてくれていた。
「新しく入った人は必ず地下に毛布を取りに行って下さい」と言っていたのである。
そんな事を知らなかった僕は、冷蔵庫のように冷えている部屋で自分のコートを布団代わりに寝るハメになった。
そんな寒さで眠れる訳もなく、ウロウロと部屋を歩き回ってみる。
すると、窓に小さな穴が空いている事に気がついた。
しかも、その穴から少しずつヒビが入っていて、目張りするには難しかった。
「この穴のせいでこんなに寒いんだ。おかげで部屋の中で遭難しそうだぞ!」
僕は穴をじっと睨んでやった。
「上等だ。僕はこんな事では負けないからな」
そんな勇ましい言葉を吐いて自分のテンションを維持させる。
しかし、寒いものは寒いので、僕は何か動く事をしようと思った。
暫く辺りを見回してみる。
体を動かす物…。
…そうだ、ピアノだ。
その部屋にはおもちゃの箱かと思うほどきゃしゃなアップライトが置いてあった。
恐る恐るその蓋を開けて、指を鍵盤に落としてみる。
「ド、レ、ミ、ソ…」
「え?」
今確かに音階が一つ抜けていた。
ドレミの次は当然ファだ。
なのに、確かに「ソ」と音が出た。
僕は絶望感に取り憑かれた。
全て鍵盤をたたいて見ると、半分くらいしか音が出なかった。
「こんなものがピアノと呼べるか!」
僕はピアノのお腹を蹴ろうとしたが、壊れそうなのでやめた。
「でも、僕が求めていたものに限りなく近い状態じゃないか」
修行がしたくて出てきたんだから、これくらいでキレてはいけない。
僕は、仕方なく、想像の中で音を鳴らしてみた。
ここはソがなっているけど、本当はファ。
ここの音は叩いても出ないけど、本当はラ。
そんな風に自分の頭の中で音をならしてみると、面白いようにイメージが広がった。
それは、誰の曲でもない、何の取り柄もない即興演奏だったが、疲れ切った僕の心を「回復」してくれる行為だった。
「今だけは寒さを忘れさせてくれ」
そんな事を願いながらピアノに向かっていると、ショパンやラフマニノフの思いが伝わってくるようで感動的だった。
やがて、瞑っていた目から自然と涙がこぼれて来た。
その涙がとても温かかった。
とても、心地よかった。
そしてその時、僕はこの旅の真の目的を悟った。
「涙するための旅だ」と。
つづく