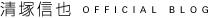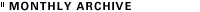越後湯沢から直江津に行く最終の特急列車内には僕とサラリーマンだけしかいなかった。
他の車両には他の客もいるのかもしれない。
「直江津までですか。わたしも直江津までです」
どうしてこのサラリーマンは僕の行き先を知っているのだろうという表情を僕が浮かべていると、
サラリーマンはアーモンド型の目を細くして気味が悪いほど爽やかな笑顔を浮かべた。
「先ほど切符が見えたのですよ。いやだなぁ、わたしはそんなに怪しいものではありませんよ。ただのサラリーマンです」
と言ってからサラリーマンは僕から目線をはずし、逆の方の窓に体ごと向きを変えた。
「でもね、ただのサラリーマンですが、もうすぐ死にます」
僕から目線をはずしたままサラリーマンは話す。
「決めてたんです。55歳でぴたりと人生を終わらせると」
55歳。
サラリーマンは見かけより歳をとっているようだ。
「中学生の時から決めていてね。わたしの人生がどんなに不幸だろうと、どんなに楽しかろうと、絶対に55歳でわたしは死ぬと」
この人は酔っていると僕は思うことにした。
「お酒は…」とサラリーマンは言いながらまたこっちに体を向けた。「…飲めませんよ」
「嫌いなんです。わたしはわたし自身の人生をコントロールしたいという強い欲求があるので、
アルコールによって自分の意見や意志を失うのは我慢ならないのです」
車掌が切符を見回りに来た。
車掌は無駄な動きを一切せずに僕の手から切符を取るとその切符にパンチを入れた。
切符を僕に返す時に小さくありがとうございますと呟いた。
まるで独り言のように。
「わたしの両親はわたしが小さい頃に死にました。そのあと親戚中をたらい回しにされました。
あの時がわたしの人生の中で一番苦しい時だった」
サラリーマンは車掌に切符を見せている間中そこに誰もいないかのように引き続き喋り続けていた。
「いやね、暴力を受けたり、酷い目に遭ったりしたわけではないのです」
列車は走り続ける。
真夜中の温泉地を。
「それはそれは親切にしてもらいましたよ。中にはそこの家族の本当の子供より大切にされていたくらいです」
僕は一度時計を見る。
直江津まではあと20分くらいある。
「でもね」とサラリーマンは言った。「耐えられなかったのです」
「あの、かわいそうな子と言わんばかりの目が。みんなわたしの事を不幸な子だと思ってくれているのです。
その悲観的な目が僕には耐えられなかった」
今度は熱いおしぼりを配りにおばちゃんが入ってくる。
おばちゃんは制服を着ているのだが、その制服のサイズがぴったりな事に僕は無償に切なさを感じた。何故だろう?
「それでわたしはある日家を持たずに路上で暮らす事にしました。ホームレスですよ。いわゆる」
サラリーマンは配られたおしぼりで顔を拭く。
「あ、いけないいけない。またこんなに自分の話をしてしまって…」
サラリーマンは本当に恥ずかしそうだった。
「すみませんね。でも今日くらいは勘弁して下さい。何せ、人生最後の日なのですから」
そう言うとサラリーマンは直江津に着くまで二度と口を開かなかった。
僕の感傷的な気分は最高潮に達した。
流れゆく景色を観ているだけで涙がこぼれそうだ。
サラリーマンはどうやって死ぬ気だろう?
僕はサラリーマンが自らの命を絶つ姿を想像して怖くなった。
そして、全てが嘘の世界なのではないかと思うほど現実離れした悲しさに襲われた。
直江津に到着すると、サラリーマンは「それではお元気で」と一言僕に告げて足早にどこかへ去ってしまった。
僕はタクシーに乗り込む。
そしてホテルに着く。
シャワーを浴びてベッドに入る。
そしてあのサラリーマンがこの街のどこかで死ぬ想像をする。
眠れない。
朝が来る。
一睡もできないまま午前中の講義へ向かう。
夏の嵐のような雨が降っている。
しかし講義が終わるまでには止んで快晴になっていた。
僕はお昼を食べてから直江津の駅へとタクシーで向かった。
越後湯沢へ行く特急が直江津駅に来るまでにはまだ30分もあった。
仕方がないので僕はホームで本でも読んで待つことにした。
しかし、紙の上で踊る活字達は僕の脳内には一つも入ってこられなかった。
僕は本をぱたりと閉めた。
あのサラリーマンはどうしたろう?
本当に死んでしまったのだろうか?
どうして55歳で死ぬと決めたのだろう?
僕は自分も55歳で死ぬと仮に決めてみた。
何かが変わった気がする。
僕の中で止まっていた時計が動き出したようにも感じた。
死がリアルになって初めて生きる心地がする。
でも、僕は死なない。
きっと、人生で守り続けなくてはいけないルールを他にみつけ、それは「生きる」という方向に繋がっているに違いない。
それにしても、あのサラリーマンのこの世のものではないような爽やかな笑顔は何だったのだろう?
そこに真の幸せがかのような。
僕は生きるという事の意味を永遠と考えていた。
直江津から越後湯沢まではあっという間だった。
何度もこの乗り換えをしたことがあるが、越後湯沢から東京行きの新幹線への連絡は面倒くさい。
なぜか、いつもそう感じる。
越後湯沢の特急が居心地いいのかもしれない。
その証拠に、東京からこっちに来る時の乗り換えにはストレスがない。
切符を3枚同時に入れ、新幹線ホームへと僕は急いだ。
僕と同じように東京方面に行く客が沢山いる。
エスカレータはその客たちの大行列になっていた。
僕は人混みが苦手だ。
東京行きの発車時刻まではあと10分ある。
もう少しここで待ってあの行列がなくなってからホームへと行こう。
僕は暫く人々を観察していた。
人々は宿命的な何かを背負っているような真剣な顔をして乗り換えをしていた。
何だか、みんな幸せそうじゃなく見えた。
若い観光客、お年寄りの温泉巡り、通勤、通学、その他色々あるだろう。
さまざまな人達が人生の「乗り換え」をしていた。
何かの実験をされているようにみんな同じ動きをしていた。
僕もきっとあの中に入ればその一員になるのだろう。
そこには「サイクル」というものがあった。
僕は怖くなった。
人々が工場で機械に一つ一つまったく同じように仕上げられていく製品のようにみえた。
僕がそうやってじっとサイクルを観ていると、知っている顔が現れた。
あのサラリーマンだった。
サラリーマンは昨日の穏やかさが嘘のように別人の顔をしていた。
深刻で暗くて切なそうで緊張しているようにみえた。
サラリーマンは昨日とまったく同じ格好でいた。
サイクルの中の一つになっていて、昨日まとっていた特有の空気は感じられなかった。
それでも僕はどこかで嬉しかった。
何が嬉しいのかよくわからなかったが、サイクルも悪くないと思えるようになった。
「生きていれば日はまた昇る」
僕はそう呟いて途絶えないエスカレータのサイクルに飛び込んでいった。
僕は夜が好きでいたい。
それには、朝を経験しなくてはいけないのだ。
朝日を知らなくては、夜の風の甘さは味わえないのだ。
こなれた感じで新幹線に飛び込んでいくサラリーマンの横顔を少し後ろから僕は見た。
昨日のような幸福感はないにしろ、何だか、ちょっと勇ましくて格好良く感じた。
東京行きの新幹線は、僕がギリギリで乗り込むとすぐに出発した。
「さぁ、帰るぞ」
と一言、僕は口に出して言ってみた。
完